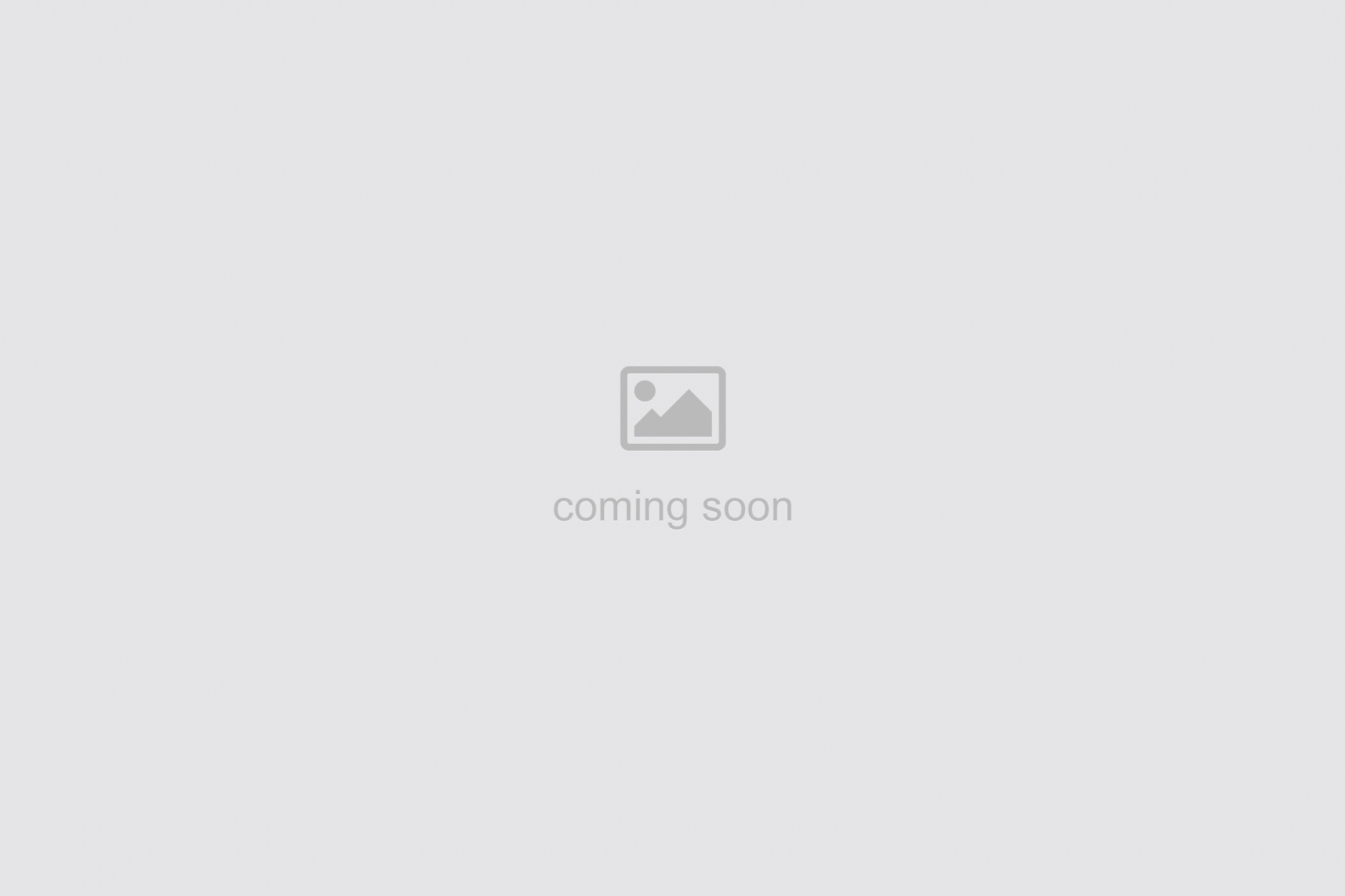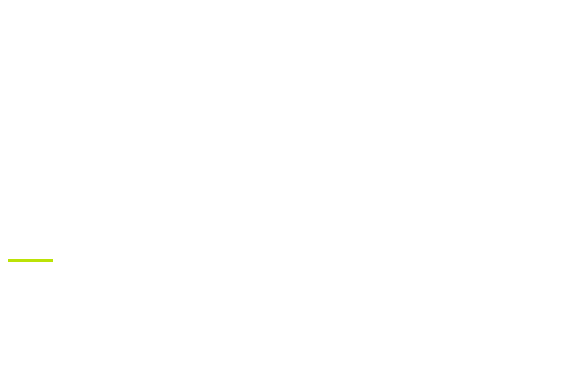「訪問数の多い時間帯」のGoogle表示の意味
2021-11-12
Googleが匿名で行なっている患者さんのGPSアンドロイド端末データやiPhoneのGoogleアプリのデータを使った「訪問数の多い時間帯」表示が、当医院の検索画面でも示されています。「平均滞在時間」も出ています。もはやこんなことができる時代なんですね。なお、「平均滞在時間」は今のところ表示が消えてしまってますが、その理由は不明です。この「混雑する時間帯」について調べたところ、スマホ端末の滞在状態を過去数ヶ月にわたったデータを平均化したものだそうです。これは施設の最も混んでいる時間帯を基準にして、混雑、やや混雑、混雑していないの3段階に分けて棒グラフで表示したもので、施設間の比較にはならないようです。実際には、診療内容や検査に時間がかかる場合も混雑するし、連休開けとか悪天候の日とかで変動しやすくなるなど、リアルタイムでは若干の食い違いもあります。リアルタイム表示の出ている施設も時々見かけますが、この理由は不明です。 棒グラフがpeakをむかえるのが後半にくる場合は待ちが長く混み合っていると解釈すべきで、パターンを見るのも面白いです。当院では1時間に10人を目標に診療を進めていますが、検査や紹介手続きなどが入ると遅れがちで、目標達成はずれ込んでしまいます。その分、平均滞在時間、平均待ち時間は延びることになります。
こうしたデータは医院が修正することも消すこともできないもので、Googleの口コミに加え混雑する時間帯についても、Googleの評価に甘んじるしかないようです。ネット界の巨大な力が下々の事業所まで目を光らせ、一般顧客に施設情報を公開しています。その評価や傾向が次第に正確に客観的に評価され、精度を上げていくでしょう。
なお、このコロナ禍にあって密を出来るだけ減らすために予約システムを導入しました。これはリアルタイムで患者の待ち人数をホームページで表示しています。すなわち、通院患者数をリアルタイムで公開していることを意味しています。勿論、患者さんが混雑を避けて通院するためのものです。平均滞在時間は表示されませんが、医院のパソコンには「平均待ち時間」の表示は出ます。ただし、この待ち時間表示は、受け付けしてから呼ばれるまでの時間となります。予約システムでは、患者さん個人では、QRコードで自分の番号はあと何人待ちで待ち時間の目安がどれだけか、携帯からホームページをみることで分かります。待合室の混雑を避けるために、一時的外出を許可しており、ネットでも確認できますし、待ち時間対策に役立っています。
この二つの表示を比較しながら、Googleの正確性と意味合いを考えるのも面白いかとーーーーーーー。