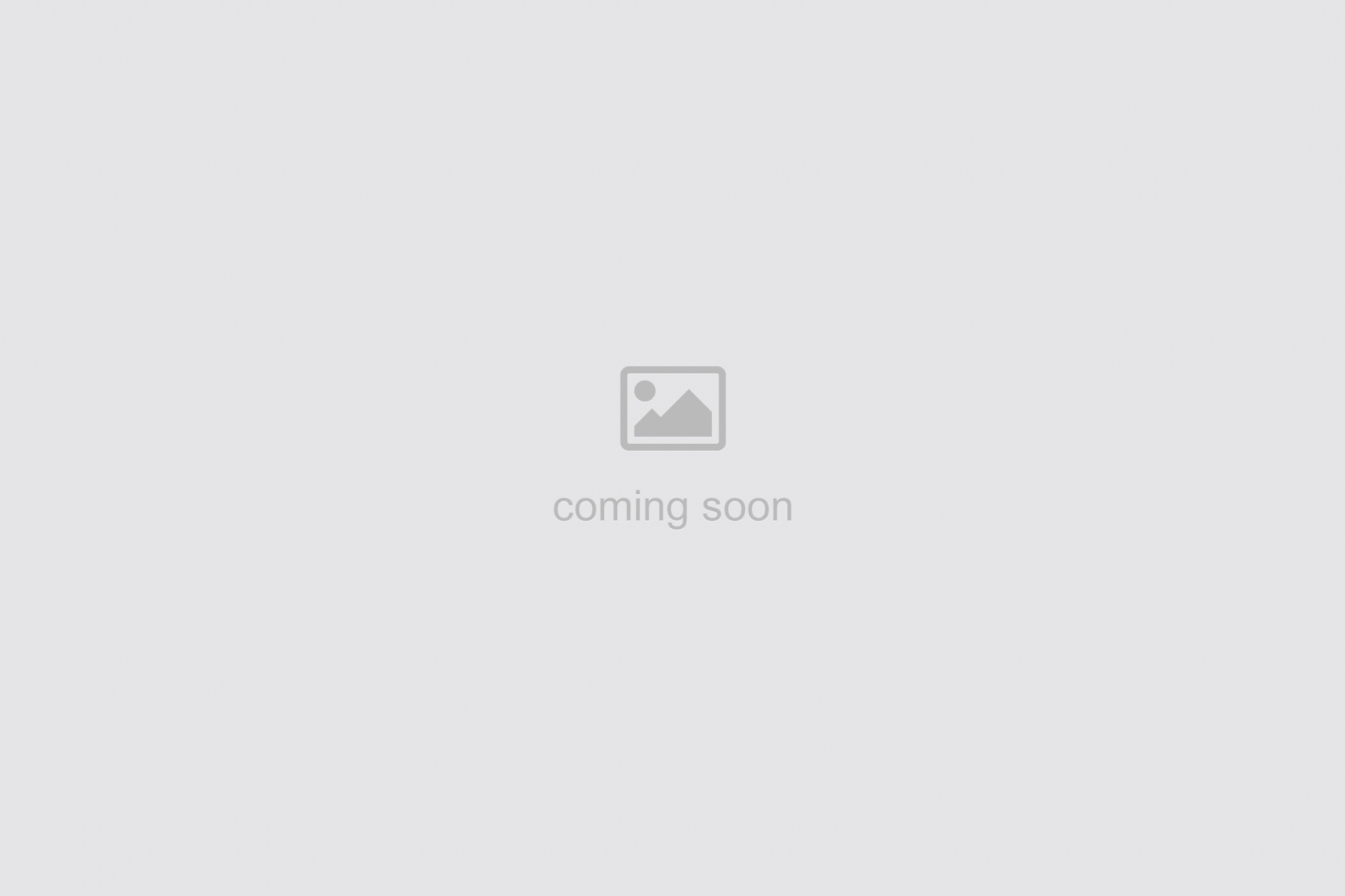血尿の種類と症状
肉眼的血尿(目で確認できる血尿)
症状 | 要因 |
ピンク色、鮮紅色の尿、ワイン色 | 多くは膀胱から尿道までに出血個所がある。 例外は、まれに大量の腎、尿管出血がある。 |
出始めから出終わりまで全部血尿の場合 | 膀胱。腎尿管の多めの出血。 |
出終わりのみ尿に血が混ざるの場合 | 膀胱三角部、頚部、後部尿道(前立腺)
膀胱の出口から外尿道括約筋部までの部分からの出血 |
下着に血が付く、尿と混ざっていないの場合
| 尿道の出口の出血、前部尿道
外尿道括約筋より尿道の出口に近い部分からの出血 |
コーヒー色、コーラ色の尿 | 多くは腎からの出血。変色。 尿との接触時間が長い場所からの出血。 |
血尿の種類と症状
顕微鏡的血尿
- 顕微鏡でしか確認できない血尿(尿検査で異常を指摘される場合)
微小血尿… 尿沈査で赤血球が強拡大(×400)で5~20個の時
無症候性血尿… 赤血球が21個以上
腎炎の疑い…尿潜血・尿蛋白のいずれも陽性である
無症候性蛋白尿…尿蛋白のみ(+)以上で尿潜血(±)以下 - 女性の場合、ある程度蓄尿した状態で尿道の出口を拭いた後、陰唇を開いて最初の尿は捨てて
真中の尿を検査にご提出ください。(中間尿の採取)
血尿の受診
肉眼的血尿の場合
系統だった検査である程度の結論、見通しを得るために直ちに泌尿器科専門施設への受診をお勧めします。
血尿が止まったからと言って何の解決にもなりません。万一癌の場合取り返しがつかないことになります。
血尿が止まったからと言って何の解決にもなりません。万一癌の場合取り返しがつかないことになります。
顕微鏡的血尿の場合
一度でもよいから、それをきっかけとして主に泌尿器科への受診をお勧めします。
多くの場合、健診で顕微的血尿(ペーパー試験 潜血陽性反応 ±、+〜)を指摘された場合、異常の有無を超音波検査でスクリーニングします。
目的は泌尿器癌、尿路結石などの発見です。
目的は泌尿器癌、尿路結石などの発見です。
その他、潜血反応の出る原因と今後の対応について指導します。
血尿の原因として考えられる症状
癌 | 膀胱癌、腎癌、腎盂・尿管癌、前立腺癌。 |
尿路結石 | 腎、腎盂、尿管、膀胱、尿道にある結石。 |
腎炎 IgA腎症 | 蛋白尿を伴いやすい。ときたま肉眼的血尿を伴う。 腎生検が必要である。 |
尿路感染症 | 白血球をともなう。膀胱炎でも多い。 わずかな異常は尿の採取方法を厳密にする。 女性には膣分泌物の混入もありうる。膣上皮。 |
腎性血尿
(特発性腎出血) | 本態性腎出血、クルミ割り現象などの腎出血。 機会的血尿 蛋白を伴わない、わずかな血尿。 薬剤性血尿 ワーファリン服用中にあり。 運動性血尿 激しいクラブ活動中の学生。剣道。多くは腎からの出血。変色。 尿との接触時間が長い場所からの出血。 |
女性と男性の違い
- 女性では40歳以上で顕微鏡的血尿は20人に一人程度の頻度でみられるといいます。ほとんどが腎性血尿ですが、まれに結石や腫瘍がみつかります。男性ではもう少し頻度は少ないようですが、まれに悪性腫瘍が発見されます。血尿は今後おこる腫瘍か結石などのサインかも知れませんので、受診のきっかけにしてください。
- 尿の異常は40~50歳を境にして増加するといわれます。腎臓の加齢現象の出現によって変化がでてくることも多いのですが、40歳以上のかたは一度は詳しい検査をお勧めします。
検査の手順
(1)まず、尿の検査で赤血球の性状、数を確認します。
(蛋白尿が強い場合、血液検査等で腎炎チェック)
(2)蓄尿時の膀胱、腎、左腎静脈の拡張の程度を超音波検査で調べます。
(ここまでの簡単チェックで経過観察も可能です。)
(3)上記で腎、尿管の異常を調べるために排泄性腎盂造影を行います。
(4)癌が否定できない場合、尿細胞診で 尿中の剥離細胞を調べておきます。
(ここまでのルーチン検査でだいたいわかります。)
(5)ルーチン検査で判定不能の場合、尿管の結石等の有無を調べるときCTスキャンを行います。
(6)腎、膀胱に「固まり」がみられたら、CTや核磁気共鳴断層法(MR)を利用します。
(ここまではほとんど無痛検査でできます。)
(7)膀胱に「固まり」を認めたり、血尿の強い場合、膀胱鏡を行います。
異常がない場合も、見落としを防ぐために、膀胱鏡をすることがあります。
例えば、繰り返す膀胱炎、薬剤抵抗性の膀胱炎様症状が続くときなどです。
血尿のそうきつくない場合は金属鏡でなく、軟性鏡で膀胱をみるとそれほど痛くありません。
気楽に受けることを希望します。但し、緊急性を要する場合や1日で結果を出さねばならない場合は、たとえ痛みを伴う検査でも速やかに受けたほうが患者さんの利益になると考えます。
施設によって手順は様々ですが、出来るだけ患者さんが無痛で精神的に楽な手順を挙げてみました。泌尿器科の敷居が高いとよく言われますが、最初からきつい検査があるのでは決してありません。担当医とよく相談しましょう。
例えば、繰り返す膀胱炎、薬剤抵抗性の膀胱炎様症状が続くときなどです。
血尿のそうきつくない場合は金属鏡でなく、軟性鏡で膀胱をみるとそれほど痛くありません。
気楽に受けることを希望します。但し、緊急性を要する場合や1日で結果を出さねばならない場合は、たとえ痛みを伴う検査でも速やかに受けたほうが患者さんの利益になると考えます。
施設によって手順は様々ですが、出来るだけ患者さんが無痛で精神的に楽な手順を挙げてみました。泌尿器科の敷居が高いとよく言われますが、最初からきつい検査があるのでは決してありません。担当医とよく相談しましょう。
強い血尿の場合
尿道、膀胱の観察が優先されます。なぜなら尿道膀胱の粘膜、左右の尿管からの流入状態の観察で出血部位を診断することができるからです。
膀胱の場合
- 膀胱腫瘍であれば、組織検査をすることになります。
- 膀胱出血、放射線後遺症など
- 膀胱炎、前立腺癌膀胱内浸潤など
後部尿道の場合
- 前立腺癌、精阜出血、前立腺炎
尿管口からの出血の場合
- 腎、尿管の検査を進めます
*高濃度の血尿の場合は、直ちに膀胱鏡がおこなわれます。
*出血が多ければ、止血手段を考える必要もあるので、多少の痛みは我慢する必要があります。
*出血が多ければ、止血手段を考える必要もあるので、多少の痛みは我慢する必要があります。
検査で経過観察となった場合
わずかな血尿が、変動乏しく同じ程度で持続する場合
恐らく腎性血尿が考えられます。この場合、長期に変化がないことを確認する必要がある。
変化があればもう一度再検討する必要あり。
変化があればもう一度再検討する必要あり。
| 蛋白を伴わない場合 | 年2回の尿チェック程度 変化の監視 赤血球の増加や変動、蛋白の出現などに注意 |
| 蛋白を多少伴う場合 | 状況に応じてチェック、NAG、蛋白定量など |
変化がない場合でも、1年後に癌の見落としが無いことをチェックするため、一連の再検査をすることがあります。
肉眼的血尿が消えた場合(腎性血尿、出血)
半年後に詳しく一連の検査で再チェック 癌の見落としが無いように!
嚢胞とか目標物がある場合
成長、変化の有無をみるため、6ヶ月に1度程度にチェック。超音波検査など。
以上の監視をある程度つづけ、異常がない場合は、そういう体質で心配がないことが確定します。
すなわち、ある程度の検査でその時点のチェックを行い、時間の経過の中で変化がないと判定することで、より完璧な診断となるわけです。血尿ばかりでなく病気や検査値異常との付き合い方、即ち距離の取り方はとても重要なことです。ただし、自分だけで独断せずに、「かかりつけ医」と相談しましょう。
すなわち、ある程度の検査でその時点のチェックを行い、時間の経過の中で変化がないと判定することで、より完璧な診断となるわけです。血尿ばかりでなく病気や検査値異常との付き合い方、即ち距離の取り方はとても重要なことです。ただし、自分だけで独断せずに、「かかりつけ医」と相談しましょう。
血尿と紛らわしい着色尿
濃縮尿
琥珀色、ウイスキー色にまでなるが、透明な尿
薬物尿
山吹色~黄色、ビタミン剤
ビリルビン尿
独特の黄褐色、肝疾患
ヘモグロビン尿、ミオグロビン尿
過激な運動の後、コーヒー色の尿が出て、赤血球がない場合